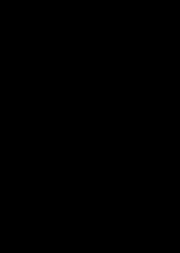第二TOKYO-revive- P6(第一章)君の名は・・・ [小説Ⅱ]
窓の外は、もううっすらと明るくなり始めていた。
正確に言えば、人工太陽TEYAN が、活動を始めたということなのだが、
日本中の皆がこれを夜明けだと信じていた。
朝日とは思えないほどの弱弱しい白い光が、高く積まれた書類に濃い影を落としている。
部屋の隅にうずくまって寝ている秋生の背中が、妙に黒く幼く見える。
時計の針はそろって真下をさし、目覚ましにとセットしていた携帯電話のアラームが、
耳に心地よい。ついさっきまでぴくりとも動かなかった秋生が体をうねらせ、
携帯電話のストラップをつかんで、自分のほうに引き寄せようとする。
斗織は手で軽く携帯電話を押さえつけ、もう片方の手で秋生の腕をつかむ。
「学校、遅刻するぞ、秋生。」
長い栗色の前髪の間から茶色の瞳がのぞき、斗織をにらむ。
「今日は休む。それと、手ぇ、痛い。」
「今日も、だろ。」
斗織は腕をつかむ力はゆるめたものの、手を放す様子をみせない。
「おまえ、出席日数ヤバイんじゃないの?」
「大丈夫だって。ほんと、だいじょーぶ。」
秋生の声がとても弱弱しい。まるで自分に言い聞かせるかのように、何度も、何度もつぶやく。
本当のところ、秋生の出席日数はとても大丈夫といえるほどではなかった。
どんなにゲーム関係の仕事が多く入ったとしても、必ず週に二、三日は登校していた秋生が、
先月からぱたりと学校に登校しなくなり、もう二ヶ月近くたつ。
普通の生徒なら、とっくに留年となっていたはずだ。
しかし、近年、アローンチルドレンの存在は両親をもつ一般の子供たちに悪い影響を及ぼし、
アローンチルドレンたち本人にもけして良い環境ではないと判断され、
「一父一母一子政策」を政府がとってきたのだ。一人の孤児に一組の里親を、という政策である。
主要都市の東京は優先的にその政策が実行されたが、
一部のアローンチルドレンたちが反発の様子をみせたのだ。
たちの悪い連中は各地で暴動を起こし、警察沙汰になるという惨状である。
秋生と斗織も、政府がうちだした政策については反対だが、
暴動を起こしてまで反発する必要は無いと思っている。
そもそも、アローンチルドレンたちが激しく反発する理由は、東京都郊外、
通称ハズレで起こったある事件からだろう。
その事件は「ハズレ、孤児狩りで死傷者出る。」と、新聞やニュースで大きくとりあげられた。
孤児狩りとは、いきすぎた政府の一父一母一子政策の皮肉をこめた言い方である。
そこまで激しい反発はなかったハズレのアローンチルドレンを、
政府が見せしめに強制収容したのだ。
その時、反発した一部のアローンチルドレンが誤って銃殺されたのだ。
ハズレは住宅地が80%を占めており、誰もがハズレはベッドタウンだと熟知していた。
そのベッドタウンで、真夜中に孤児狩りなど、とんでもない。ましてや、死傷者を出すなど。
そう言って世間は政府を攻め立て、その勢いでアローンチルドレンが騒ぎはじめたのだ。
学校に来ていたアローンチルドレンたちも、しばらくは雲隠れすると言って、
休学届けを出す者も多かった。休学届けも連絡もなしに、
無断欠席するアローンチルドレンもしばしばいる為、秋生はまだ大目に見てもらっているのだ。
「だいじょう・・・ぶ、だからさ。ほんとに・・・」
秋生の瞳から大粒の涙が零れ落ち、頬を伝う。気づけば、かすかに肩も震えている。
今までずっと秋生とつるんできたが、斗織はこんなに弱った秋生を見たことがなかった。
普段年齢不相応なほどにたくましく、斗織をも圧倒する迫力をもつ秋生が、とても弱く、幼く見える。
世界には今、秋生と自分、二人だけしか存在しないかのように思われて、斗識は心がすくんだ。
正確に言えば、人工太陽TEYAN が、活動を始めたということなのだが、
日本中の皆がこれを夜明けだと信じていた。
朝日とは思えないほどの弱弱しい白い光が、高く積まれた書類に濃い影を落としている。
部屋の隅にうずくまって寝ている秋生の背中が、妙に黒く幼く見える。
時計の針はそろって真下をさし、目覚ましにとセットしていた携帯電話のアラームが、
耳に心地よい。ついさっきまでぴくりとも動かなかった秋生が体をうねらせ、
携帯電話のストラップをつかんで、自分のほうに引き寄せようとする。
斗織は手で軽く携帯電話を押さえつけ、もう片方の手で秋生の腕をつかむ。
「学校、遅刻するぞ、秋生。」
長い栗色の前髪の間から茶色の瞳がのぞき、斗織をにらむ。
「今日は休む。それと、手ぇ、痛い。」
「今日も、だろ。」
斗織は腕をつかむ力はゆるめたものの、手を放す様子をみせない。
「おまえ、出席日数ヤバイんじゃないの?」
「大丈夫だって。ほんと、だいじょーぶ。」
秋生の声がとても弱弱しい。まるで自分に言い聞かせるかのように、何度も、何度もつぶやく。
本当のところ、秋生の出席日数はとても大丈夫といえるほどではなかった。
どんなにゲーム関係の仕事が多く入ったとしても、必ず週に二、三日は登校していた秋生が、
先月からぱたりと学校に登校しなくなり、もう二ヶ月近くたつ。
普通の生徒なら、とっくに留年となっていたはずだ。
しかし、近年、アローンチルドレンの存在は両親をもつ一般の子供たちに悪い影響を及ぼし、
アローンチルドレンたち本人にもけして良い環境ではないと判断され、
「一父一母一子政策」を政府がとってきたのだ。一人の孤児に一組の里親を、という政策である。
主要都市の東京は優先的にその政策が実行されたが、
一部のアローンチルドレンたちが反発の様子をみせたのだ。
たちの悪い連中は各地で暴動を起こし、警察沙汰になるという惨状である。
秋生と斗織も、政府がうちだした政策については反対だが、
暴動を起こしてまで反発する必要は無いと思っている。
そもそも、アローンチルドレンたちが激しく反発する理由は、東京都郊外、
通称ハズレで起こったある事件からだろう。
その事件は「ハズレ、孤児狩りで死傷者出る。」と、新聞やニュースで大きくとりあげられた。
孤児狩りとは、いきすぎた政府の一父一母一子政策の皮肉をこめた言い方である。
そこまで激しい反発はなかったハズレのアローンチルドレンを、
政府が見せしめに強制収容したのだ。
その時、反発した一部のアローンチルドレンが誤って銃殺されたのだ。
ハズレは住宅地が80%を占めており、誰もがハズレはベッドタウンだと熟知していた。
そのベッドタウンで、真夜中に孤児狩りなど、とんでもない。ましてや、死傷者を出すなど。
そう言って世間は政府を攻め立て、その勢いでアローンチルドレンが騒ぎはじめたのだ。
学校に来ていたアローンチルドレンたちも、しばらくは雲隠れすると言って、
休学届けを出す者も多かった。休学届けも連絡もなしに、
無断欠席するアローンチルドレンもしばしばいる為、秋生はまだ大目に見てもらっているのだ。
「だいじょう・・・ぶ、だからさ。ほんとに・・・」
秋生の瞳から大粒の涙が零れ落ち、頬を伝う。気づけば、かすかに肩も震えている。
今までずっと秋生とつるんできたが、斗織はこんなに弱った秋生を見たことがなかった。
普段年齢不相応なほどにたくましく、斗織をも圧倒する迫力をもつ秋生が、とても弱く、幼く見える。
世界には今、秋生と自分、二人だけしか存在しないかのように思われて、斗識は心がすくんだ。
第二TOKYO-revive-(第一章)P5君の名は・・・ [小説Ⅱ]
第二TOKYO-revive-
第一章 君の名は・・・
電気の消えた、いや、故意に消された斗織の研究室に、キーボードをたたく音が響いている。
明かりといえば、パソコンから発せられる光と、卓上ランプの白すぎるほどの光だけだった。
薄暗い研究室に、長細い光の影が落とされる。自動ドアの機械音が不気味なほどに強く低く響いた。
「斗織、解析終わったか?」
「あぁ。」
キーボードをたたく手を止めず、秋生の問いかけに答える。
研究室という堅苦しい場所には似合わない、ピンクのマグカップが事務机におかれ、
なみなみと注がれたコーヒーに、卓上ランプの光が鈍く反射していた。
ピンクのマグカップは斗織の趣味ではなく、あの新米研究員からのプレゼントで、
露骨に好意を感じさせるものだった。
「知ってるか、日本の外では、夜には空に星が見えるんだとよ。」
秋生が突然妙なことを言い出すものだから、斗織は思わず苦笑してしまった。
2486年四月九日、核爆弾戦争終結。以後、非参加国の日本以外の国の土地は60%が砂漠化し、
放射線に汚染された。放射線から日本を守るため、2486年七月九日、日本ドーム化計画発動。
2490年には、日本は完全にドームに包まれていた。
空が恋しい、誰もが一度はそう思い、激動の世界の中で、その思いは消えていった。
教育機関では、空・海・風・星・その他の自然の知識を子供たちに与えることをしなくなり、
核爆弾戦争終結から百年たった今では、自然の知識を持つものは、
大人子供を含め一握りの人間だけだった。
人工太陽が輝く日中で、秋生がそんなことを言えば、間違いなく斗織は笑い飛ばしていたことだろう。
しかし、人に染み込んだ本能というやつだろうか、人は暗闇で光を、星を求める。
もちろん、秋生と斗織も例外ではなかった。自然に対する興味が無いわけではなく、
与えられる知識が少なすぎて、想像というものすらできないのだ。
子供は不思議に思い、大人に質問し、大人は理由も述べずに子供たちを押さえつける。
それが余計に、子供たちの関心や興味を煽ると、大人たちはいい加減学習すべきであろう。
日本には謎と秘密が多すぎて、それを隠す大人に子供が不信感を抱く。
そうして、けしてポジティブではない気持ちを隠すため、紛らわせるために、
子供たちの中ではゲームが流行り、執着し、今のようなゲーム社会がうまれたのだ。
斗織は、秋生の言葉が、子供たちの思いの象徴のように感じられてならなかった。
第一章 君の名は・・・
電気の消えた、いや、故意に消された斗織の研究室に、キーボードをたたく音が響いている。
明かりといえば、パソコンから発せられる光と、卓上ランプの白すぎるほどの光だけだった。
薄暗い研究室に、長細い光の影が落とされる。自動ドアの機械音が不気味なほどに強く低く響いた。
「斗織、解析終わったか?」
「あぁ。」
キーボードをたたく手を止めず、秋生の問いかけに答える。
研究室という堅苦しい場所には似合わない、ピンクのマグカップが事務机におかれ、
なみなみと注がれたコーヒーに、卓上ランプの光が鈍く反射していた。
ピンクのマグカップは斗織の趣味ではなく、あの新米研究員からのプレゼントで、
露骨に好意を感じさせるものだった。
「知ってるか、日本の外では、夜には空に星が見えるんだとよ。」
秋生が突然妙なことを言い出すものだから、斗織は思わず苦笑してしまった。
2486年四月九日、核爆弾戦争終結。以後、非参加国の日本以外の国の土地は60%が砂漠化し、
放射線に汚染された。放射線から日本を守るため、2486年七月九日、日本ドーム化計画発動。
2490年には、日本は完全にドームに包まれていた。
空が恋しい、誰もが一度はそう思い、激動の世界の中で、その思いは消えていった。
教育機関では、空・海・風・星・その他の自然の知識を子供たちに与えることをしなくなり、
核爆弾戦争終結から百年たった今では、自然の知識を持つものは、
大人子供を含め一握りの人間だけだった。
人工太陽が輝く日中で、秋生がそんなことを言えば、間違いなく斗織は笑い飛ばしていたことだろう。
しかし、人に染み込んだ本能というやつだろうか、人は暗闇で光を、星を求める。
もちろん、秋生と斗織も例外ではなかった。自然に対する興味が無いわけではなく、
与えられる知識が少なすぎて、想像というものすらできないのだ。
子供は不思議に思い、大人に質問し、大人は理由も述べずに子供たちを押さえつける。
それが余計に、子供たちの関心や興味を煽ると、大人たちはいい加減学習すべきであろう。
日本には謎と秘密が多すぎて、それを隠す大人に子供が不信感を抱く。
そうして、けしてポジティブではない気持ちを隠すため、紛らわせるために、
子供たちの中ではゲームが流行り、執着し、今のようなゲーム社会がうまれたのだ。
斗織は、秋生の言葉が、子供たちの思いの象徴のように感じられてならなかった。
第二TOKYO-revive-(第一章)P4君の名は・・・ [小説Ⅱ]
第二TOKYO-revive-
第一章 君の名は・・・
「困りますよ、天野さん。こんなことされちゃあ。」
斗織は顔の前で手を合わせながら、軽く頭を下げる。
それになだめられたように、研究員の一人らしき女の顔がゆるむ。
まだ少女のようなあどけなさを残した新米研究員に、今日ばかりは頭が上がらなかった。
「今回だけですからね。」
研究員は、そう言ってカードキーを斗織の手に握らせると、肩をすくめて見せた。
研究員が立ち去るのを確認してから、斗織は物陰に隠れていた秋生を呼び寄せる。
巴を背負った秋生の背中には、うっすらと汗が滲んでいた。斗織には、
それが暑さによるものからなのか、それとも緊張といった部類からくるものなのか分からなかった。
あの場にいた誰もが、いや、正確には秋生と斗織は、銃声の直後、
巴の胸から流れ落ちる紅い鮮血を予感した。しかし、
実際には巴の服を裂いただけで、予感した風景が斗織の目の前に広がることはなかった。
巴の胸に命中した銃丸は、機能を停止させる能力はあっても、身体を打ち砕く威力はなかったようだ。
巴は、一瞬驚愕の表情をみせ、すぐに機能を停止した。あれから約一時間後、
斗織がサンプル保管の名目で自分の研究室の研究員を呼び出し、
巴を密かに研究所まで運んだのだ。正確に言うと自分の研究所ではなく、
アトライズ株式会社の研究所だが。秋生は、けして頭の悪いほうではない。
どちらかといえば、かなり専門的なことまで理解できるほど賢かった。
しかし、斗織の尋常でないほどの専門的知識には、とても及ばなかった。
斗織は、巴の胸元にある十字架の刺青だけで、巴がオートマタだと判断した。
銃弾の摩擦によって焼け爛れた人工の皮膚がはがれて、
中からいかにも硬そうな金属がのぞいていたからだ。
昔はどうだか分からないが、今現在日本国で製造されているオートマタには、
十字架の刺青を入れるという異様な習慣が染み付いていた。
見たところ、どこのメーカーの刺青とも一致しなかったため、
オリジナルで作られたものだろうと推測される。
あの要という男が、巴を作ったのだろう。
いくら自分で作った全自動コンピューターだからといっても、
こんな使い方をすることについて、斗織は少なからず尊敬の念だけは抱けないだろうと思った。
第一章 君の名は・・・
「困りますよ、天野さん。こんなことされちゃあ。」
斗織は顔の前で手を合わせながら、軽く頭を下げる。
それになだめられたように、研究員の一人らしき女の顔がゆるむ。
まだ少女のようなあどけなさを残した新米研究員に、今日ばかりは頭が上がらなかった。
「今回だけですからね。」
研究員は、そう言ってカードキーを斗織の手に握らせると、肩をすくめて見せた。
研究員が立ち去るのを確認してから、斗織は物陰に隠れていた秋生を呼び寄せる。
巴を背負った秋生の背中には、うっすらと汗が滲んでいた。斗織には、
それが暑さによるものからなのか、それとも緊張といった部類からくるものなのか分からなかった。
あの場にいた誰もが、いや、正確には秋生と斗織は、銃声の直後、
巴の胸から流れ落ちる紅い鮮血を予感した。しかし、
実際には巴の服を裂いただけで、予感した風景が斗織の目の前に広がることはなかった。
巴の胸に命中した銃丸は、機能を停止させる能力はあっても、身体を打ち砕く威力はなかったようだ。
巴は、一瞬驚愕の表情をみせ、すぐに機能を停止した。あれから約一時間後、
斗織がサンプル保管の名目で自分の研究室の研究員を呼び出し、
巴を密かに研究所まで運んだのだ。正確に言うと自分の研究所ではなく、
アトライズ株式会社の研究所だが。秋生は、けして頭の悪いほうではない。
どちらかといえば、かなり専門的なことまで理解できるほど賢かった。
しかし、斗織の尋常でないほどの専門的知識には、とても及ばなかった。
斗織は、巴の胸元にある十字架の刺青だけで、巴がオートマタだと判断した。
銃弾の摩擦によって焼け爛れた人工の皮膚がはがれて、
中からいかにも硬そうな金属がのぞいていたからだ。
昔はどうだか分からないが、今現在日本国で製造されているオートマタには、
十字架の刺青を入れるという異様な習慣が染み付いていた。
見たところ、どこのメーカーの刺青とも一致しなかったため、
オリジナルで作られたものだろうと推測される。
あの要という男が、巴を作ったのだろう。
いくら自分で作った全自動コンピューターだからといっても、
こんな使い方をすることについて、斗織は少なからず尊敬の念だけは抱けないだろうと思った。
第二TOKYO-revive-(第一章)P3君の名は・・・ [小説Ⅱ]
第二TOKYO-revive-
第一章 君の名は・・・
「おまえたち、何者だ?」
いつにもまして、低い声で斗織が言葉を発した。右手には拳銃が握られている。
「相手の正体を尋ねる時は自分からって、教わらなかったか、坊主。」
憮然な態度で応じる男に向かって、斗織は拳銃を構える。
「どうせ、調べて知ってるんだろう?これ以上俺らの何が知りたいって?」
「フェアじゃないよなぁ。お嬢ちゃんも、そう思うだろ?」
場の空気に似合わず、ふざけた口調で秋生が言うと、男がゆっくりと斗織に近づく。
銃口が胸にあたるほど近くに来て止まり、まじまじと斗織の顔をながめる。
「気に入った。俺は要(カナメ)、そっちは巴。GSTRのブラッド・オブ・ザ・レッドのボスと補佐。
アースの指示で、天野斗織を監視していた。」
斗織には、何を言っているのかさっぱり分からないようだったが、
秋生はまったくと言っていいほど逆の反応をみせた。
普段真剣な顔などめったに見せない秋生が、真剣な顔をしている。
斗織はそれだけで、とんでもないことに巻き込まれたのだと察知したが、もう遅かった。
要と名乗った男はその一瞬の隙を見て、ふところに隠し持っていた拳銃を取り出し、
引きがねを引く。鈍い金属音と共に、秋生の腕から巴がずり落ちる。
「今日はここらで切り上げるが、次は本気でかかってこいよ、坊主ども。」
不気味ながらも品のある笑いを浮かべながら、要は斗織から離れ、歩き出す。
秋生がとっさに要に銃を向けるが、要は声を立てて笑いながら、なおも歩みを止めようとしなかった。
「アシュ・グレイの幹部も、落ちたもんだなぁ、キオ。」
秋生の瞳は羞恥と憎悪に染まり、斗織は、おぞましさが背中をかけのぼるのを確かに感じた。
斗織と秋生は、要が柱の影の闇に消えるまで、声帯さえも自由にすることができなかった。
第一章 君の名は・・・
「おまえたち、何者だ?」
いつにもまして、低い声で斗織が言葉を発した。右手には拳銃が握られている。
「相手の正体を尋ねる時は自分からって、教わらなかったか、坊主。」
憮然な態度で応じる男に向かって、斗織は拳銃を構える。
「どうせ、調べて知ってるんだろう?これ以上俺らの何が知りたいって?」
「フェアじゃないよなぁ。お嬢ちゃんも、そう思うだろ?」
場の空気に似合わず、ふざけた口調で秋生が言うと、男がゆっくりと斗織に近づく。
銃口が胸にあたるほど近くに来て止まり、まじまじと斗織の顔をながめる。
「気に入った。俺は要(カナメ)、そっちは巴。GSTRのブラッド・オブ・ザ・レッドのボスと補佐。
アースの指示で、天野斗織を監視していた。」
斗織には、何を言っているのかさっぱり分からないようだったが、
秋生はまったくと言っていいほど逆の反応をみせた。
普段真剣な顔などめったに見せない秋生が、真剣な顔をしている。
斗織はそれだけで、とんでもないことに巻き込まれたのだと察知したが、もう遅かった。
要と名乗った男はその一瞬の隙を見て、ふところに隠し持っていた拳銃を取り出し、
引きがねを引く。鈍い金属音と共に、秋生の腕から巴がずり落ちる。
「今日はここらで切り上げるが、次は本気でかかってこいよ、坊主ども。」
不気味ながらも品のある笑いを浮かべながら、要は斗織から離れ、歩き出す。
秋生がとっさに要に銃を向けるが、要は声を立てて笑いながら、なおも歩みを止めようとしなかった。
「アシュ・グレイの幹部も、落ちたもんだなぁ、キオ。」
秋生の瞳は羞恥と憎悪に染まり、斗織は、おぞましさが背中をかけのぼるのを確かに感じた。
斗織と秋生は、要が柱の影の闇に消えるまで、声帯さえも自由にすることができなかった。
第二TOKYO-revive-(第一章)P2君の名は・・・ [小説Ⅱ]
第二TOKYO-revive-
第一章 君の名は・・・
「緑がかった金髪の男が天野斗織(アマノトシキ)、トウキョウ区ゲーム選手権三年連続優勝。
アトライズ株式会社のゲームテスターでありながら、
トイビート株式会社でゲームプロジェクターも務める凄腕ゲーマー。
栗色の髪の男が松田秋生(マツダアキオ)大会等では目立った功績は無し。
しかしGSTRでは、一年前に解散したアシュ・グレイの幹部をつとめ、
最近になってアシュ・グレイのメンバーを召集し、改アシュ・グレイの再建につくしている・・・」
ライフルを標的に向けたまま、一人の少女が仲間らしき男にむかって一方的に話し続けている。
彼女の淡々とした口調から、ロボットやコンピュータのような雰囲気を感じずにはいられない。
整った顔立ちと、漆黒のおかっぱ頭から、おそらく誰もが日本人形を連想してしまうだろう。
鈍く光るライフルと、黒く底光りする髪が、彼女の魅力を一層引き立てている。
しばらく続いた沈黙を壊すように、もう一人の男が言葉を発した。
「あいつをGSTRに引き込むのは、可能だと思うか、巴。」
巴と呼ばれた少女が、一瞬表情を曇らせ、不安そうに男の方を見やる。
「珍しく弱気ですね、ボス。」
さっきまでの自信に満ち溢れた表情から一転し、巴の顔は凍り付いていた。
自分が信じる絶対的な人物が、今、自分のスコープの中にいる少年を恐れているように見えるのだ。
動揺と共に、深い嫌悪感に襲われる。
「見失うぞ、巴。」
低く呟かれた言葉には少しだけ力がこもっていて、巴は小さな恐怖さえ覚えたほどだった。
スコープに目を戻すと、ついさっきまでスコープでとらえていた標的が消えていた。
慌てて周りを探すが、それらしい人影一つ見つからない。
「くっ・・・、すいません、見失いました。」
巴の言葉に追い討ちをかけるかのように、秋生が荒い息を整えながら答えた。
「見失っちゃあいないぜ、お嬢さん。」
声と同時に、巴の頭に冷たいものがあてられる。巴は一瞬で身を硬くした。
第一章 君の名は・・・
「緑がかった金髪の男が天野斗織(アマノトシキ)、トウキョウ区ゲーム選手権三年連続優勝。
アトライズ株式会社のゲームテスターでありながら、
トイビート株式会社でゲームプロジェクターも務める凄腕ゲーマー。
栗色の髪の男が松田秋生(マツダアキオ)大会等では目立った功績は無し。
しかしGSTRでは、一年前に解散したアシュ・グレイの幹部をつとめ、
最近になってアシュ・グレイのメンバーを召集し、改アシュ・グレイの再建につくしている・・・」
ライフルを標的に向けたまま、一人の少女が仲間らしき男にむかって一方的に話し続けている。
彼女の淡々とした口調から、ロボットやコンピュータのような雰囲気を感じずにはいられない。
整った顔立ちと、漆黒のおかっぱ頭から、おそらく誰もが日本人形を連想してしまうだろう。
鈍く光るライフルと、黒く底光りする髪が、彼女の魅力を一層引き立てている。
しばらく続いた沈黙を壊すように、もう一人の男が言葉を発した。
「あいつをGSTRに引き込むのは、可能だと思うか、巴。」
巴と呼ばれた少女が、一瞬表情を曇らせ、不安そうに男の方を見やる。
「珍しく弱気ですね、ボス。」
さっきまでの自信に満ち溢れた表情から一転し、巴の顔は凍り付いていた。
自分が信じる絶対的な人物が、今、自分のスコープの中にいる少年を恐れているように見えるのだ。
動揺と共に、深い嫌悪感に襲われる。
「見失うぞ、巴。」
低く呟かれた言葉には少しだけ力がこもっていて、巴は小さな恐怖さえ覚えたほどだった。
スコープに目を戻すと、ついさっきまでスコープでとらえていた標的が消えていた。
慌てて周りを探すが、それらしい人影一つ見つからない。
「くっ・・・、すいません、見失いました。」
巴の言葉に追い討ちをかけるかのように、秋生が荒い息を整えながら答えた。
「見失っちゃあいないぜ、お嬢さん。」
声と同時に、巴の頭に冷たいものがあてられる。巴は一瞬で身を硬くした。
第二TOKYO-revive-(第一章)P1君の名は・・・ [小説Ⅱ]
おひさしぶりです!小説は?早く更新しろよ!
と怒られましたので、更新しようかな~、なんてね。
ま、色々と心配おかけしましたが、復活しました!
これからもどうぞよろしくお願いします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第二TOKYO-revive-
第一章 君の名は・・・
「ね**知っ*る?***空は青***すって。」
空が青いはずがないだろう。だって空は、灰色で暗いんだ。誰もがそう学校で習ったさ。
「きっと***たちは**こに***いけ***だわ。」
え?聞こえない。何て言ってるんだ?
「だか***きっ*帰りた*****うのよ。」
お願い、まって!もう一度言って!せめて君の名前を・・・
「君の名前は!」
「俺の名前?松田秋生、キオって呼んで。」
「・・・・・・」
頭がボーっとする。珍しく夢をみていたのに、秋生のせいでだいなしになってしまった。
視界にかかる前髪をかきあげると、まだ秋生が俺の顔を覗き込んでいることに気付く。
「大丈夫か?珍しいな、シキが夢をみるなんて。」
俺が夢みちゃ悪いってのかよ、と思いながらも、あえて斗織は口に出さなかった。
「それより、コードネームで呼ぶなよ、秋生。」
秋生は、俺が眠りこける前まで飲んでいた、おそらく炭酸がぬけているだろうと思われる
コーラのビンに手をのばした。よほど喉が渇いていたのか、半分ほど残っていたコーラを
一気に飲み干すと、マズイと文句を言いながら、俺の肩に寄りかかってくる。
「向かいのビルに二人、ライフルもってるぜ。どうする?」
斗織はなるほどと思いながら苦笑した。俺にどうすると言われてもこまるのだが、しかたがない。
いつもこんな調子で騒ぎに巻き込まれるものだから、もう慣れてしまった。
腰に隠していた拳銃もどきに手をかけ、今もなお、俺に寄りかかっている秋生の腰に手を回す。
どうやら秋生も拳銃もどきを持っているようだった。
「何したんだよ、おまえ。」
「知るかよそんなの。」
少し怒った口調で言いながら、秋生は歩き出す。路地裏におびき寄せるつもりなのだろうか、
来いよ、と秋生が身振りで示す。指示どうりに付いていくことにし、俺達は足早にこの場を離れた。
と怒られましたので、更新しようかな~、なんてね。
ま、色々と心配おかけしましたが、復活しました!
これからもどうぞよろしくお願いします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第二TOKYO-revive-
第一章 君の名は・・・
「ね**知っ*る?***空は青***すって。」
空が青いはずがないだろう。だって空は、灰色で暗いんだ。誰もがそう学校で習ったさ。
「きっと***たちは**こに***いけ***だわ。」
え?聞こえない。何て言ってるんだ?
「だか***きっ*帰りた*****うのよ。」
お願い、まって!もう一度言って!せめて君の名前を・・・
「君の名前は!」
「俺の名前?松田秋生、キオって呼んで。」
「・・・・・・」
頭がボーっとする。珍しく夢をみていたのに、秋生のせいでだいなしになってしまった。
視界にかかる前髪をかきあげると、まだ秋生が俺の顔を覗き込んでいることに気付く。
「大丈夫か?珍しいな、シキが夢をみるなんて。」
俺が夢みちゃ悪いってのかよ、と思いながらも、あえて斗織は口に出さなかった。
「それより、コードネームで呼ぶなよ、秋生。」
秋生は、俺が眠りこける前まで飲んでいた、おそらく炭酸がぬけているだろうと思われる
コーラのビンに手をのばした。よほど喉が渇いていたのか、半分ほど残っていたコーラを
一気に飲み干すと、マズイと文句を言いながら、俺の肩に寄りかかってくる。
「向かいのビルに二人、ライフルもってるぜ。どうする?」
斗織はなるほどと思いながら苦笑した。俺にどうすると言われてもこまるのだが、しかたがない。
いつもこんな調子で騒ぎに巻き込まれるものだから、もう慣れてしまった。
腰に隠していた拳銃もどきに手をかけ、今もなお、俺に寄りかかっている秋生の腰に手を回す。
どうやら秋生も拳銃もどきを持っているようだった。
「何したんだよ、おまえ。」
「知るかよそんなの。」
少し怒った口調で言いながら、秋生は歩き出す。路地裏におびき寄せるつもりなのだろうか、
来いよ、と秋生が身振りで示す。指示どうりに付いていくことにし、俺達は足早にこの場を離れた。
第二TOKYO-revive-(序章) [小説Ⅱ]
第二TOKYO-revive-
2486年、核爆弾戦争、終結。ほとんどの大陸が放射能に汚染され、
核爆弾戦争に参加しなかった日本だけが、その被害をまぬがれていた。
ごく少数のアメリカ人が日本に避難してきただけで、
世界で生き残った人種はアメリカ人と日本人だけだった。
それから、自給自足を求められた日本は、驚くべき発展をとげていった。
食料の生産、収穫はすべてロボットが管理し、飢えた国民などどこを探してもいなかった。
隔離された日本の中は平和そのものだった。
そんな中、子供達が密かに集まり、ある一つのゲームに夢中になった。
「ゲーム第二TOKYO-revive-」通称GSTRは、トーキョータワー、
フェアリーアイランド、ハズレ、アンノウンの四ヶ所から発信されている電波を
パソコンでキャッチすることによって遊べる、RPGのことである。
電波が発信されているその四ヶ所はすべてトウキョウの中にあり、
ハズレは郊外のはずれ、アンノウンは文字通りどこにあるか不明となっている。
トーキョータワーとフェアリーアイランドは人口密集区にあるため、
一番プレイヤー数が多いことでも有名だ。GSTRはグループで戦うゲームで、
一グループにつき一人のボスがいる。グループの戦い方は様々で、
おもにボスの性格や人格にさようされていると言っても過言ではない。
有名なグループは「ブラッド・オブ・ザ・レッド」「ホーリー・ホワイツ」「サンライズ・イエロー」
「アズ・ブラック・アズ」「シーズ・ブルー」の五つ。
ニックネームは、本名の字の中からコンピューターがランダム登録し、
グループのボスになるとニックネーム変更が可能となり、好きなニックネームを登録できる。
ただし、ボスになるとニックネームは漢字にしなければならない。
ゲームの舞台は2586年、今から百年後のトウキョウ。
ゲームをクリアするためには、第二TOKYO-revive-にたどりつき、
ゲームマスターのリヴァイヴを倒さなくてはならない。
さあ、探せ!そこに答えが待っている!嘘にまみれた世界から、自分たちの生きる未来を取り戻せ!
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
新しい小説の予告編みたいなものです。
一応、リヴリーも出てきます。(擬人化で)
2486年、核爆弾戦争、終結。ほとんどの大陸が放射能に汚染され、
核爆弾戦争に参加しなかった日本だけが、その被害をまぬがれていた。
ごく少数のアメリカ人が日本に避難してきただけで、
世界で生き残った人種はアメリカ人と日本人だけだった。
それから、自給自足を求められた日本は、驚くべき発展をとげていった。
食料の生産、収穫はすべてロボットが管理し、飢えた国民などどこを探してもいなかった。
隔離された日本の中は平和そのものだった。
そんな中、子供達が密かに集まり、ある一つのゲームに夢中になった。
「ゲーム第二TOKYO-revive-」通称GSTRは、トーキョータワー、
フェアリーアイランド、ハズレ、アンノウンの四ヶ所から発信されている電波を
パソコンでキャッチすることによって遊べる、RPGのことである。
電波が発信されているその四ヶ所はすべてトウキョウの中にあり、
ハズレは郊外のはずれ、アンノウンは文字通りどこにあるか不明となっている。
トーキョータワーとフェアリーアイランドは人口密集区にあるため、
一番プレイヤー数が多いことでも有名だ。GSTRはグループで戦うゲームで、
一グループにつき一人のボスがいる。グループの戦い方は様々で、
おもにボスの性格や人格にさようされていると言っても過言ではない。
有名なグループは「ブラッド・オブ・ザ・レッド」「ホーリー・ホワイツ」「サンライズ・イエロー」
「アズ・ブラック・アズ」「シーズ・ブルー」の五つ。
ニックネームは、本名の字の中からコンピューターがランダム登録し、
グループのボスになるとニックネーム変更が可能となり、好きなニックネームを登録できる。
ただし、ボスになるとニックネームは漢字にしなければならない。
ゲームの舞台は2586年、今から百年後のトウキョウ。
ゲームをクリアするためには、第二TOKYO-revive-にたどりつき、
ゲームマスターのリヴァイヴを倒さなくてはならない。
さあ、探せ!そこに答えが待っている!嘘にまみれた世界から、自分たちの生きる未来を取り戻せ!
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
新しい小説の予告編みたいなものです。
一応、リヴリーも出てきます。(擬人化で)